A.
はい。「片頭痛」などの機能性頭痛は、神経内科医の専門分野です。
「頭痛外来」という名称は、医療機関が患者さまに診療体制をわかりやすくするための呼び方として広く使われていますが、医学的に正式な診療科名ではありませんので、当院では使用しておりません。
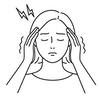
頭痛


よくある質問
患者さまからよくお伺いする質問と、
その回答をカテゴリー別にまとめてみました。
ご不明な点がございましたら、
お気軽に当院までお問い合わせください。
A.
はい。「片頭痛」などの機能性頭痛は、神経内科医の専門分野です。
「頭痛外来」という名称は、医療機関が患者さまに診療体制をわかりやすくするための呼び方として広く使われていますが、医学的に正式な診療科名ではありませんので、当院では使用しておりません。
A.
頭痛の頻度や程度によりますが、日常生活に支障をきたす場合や、症状が改善しない場合は、早めの受診をおすすめします。
A.
検査内容によりますが、MRI検査は約15分程度です。
→「MRI」についてもっとくわしく
A.
はい、あります。MRIだけでは判断が難しい症状もありますので、神経内科専門医による診察を受けることで、原因の特定につながる可能性があります。
→「頭痛」についてもっとくわしく
A.
はい、糖尿病性末梢神経障害がしびれの原因となることがあります。血糖のコントロールが重要です。
A.
MRI検査、神経生理検査(神経伝導検査・筋電図)などを、必要に応じて組み合わせます。
A.
はい、しびれは重大な病気の初期症状であることもあります。気になる症状があればご相談ください。
A4.
一時的な改善でも、繰り返すむせがある場合は再発予防の観点から定期的な確認が大切です。
A.
はい、ふるえは神経内科でよく扱う症状の一つです。お気軽にご相談ください。
むせる場合も違和感を感じた時点でご相談ください。耳鼻科的な異常がなくても、神経性の可能性があります。
A.
いいえ、本態性振戦や内科疾患、薬剤性など、ふるえの原因は多岐にわたります。専門的な診断が重要です。
A.
年齢に伴うものもありますが、ひどくなっている場合や、日常生活に支障をきたす場合は、神経内科の受診をおすすめします。
よくむせる場合は、病的な嚥下障害の可能性もあるため、評価する価値があります。
A.
詳細な問診の後、 認知機能テスト、MRIによる画像検査、血液検査など、症状に応じた検査を行います。
A.
はい、甲状腺機能低下症など原因が特定できれば、治療によって改善するものもあります。
A1.
加齢による自然なもの忘れは、生活に支障をきたさない範囲ですが、認知症では生活全般に影響が及びます。診断には専門的な評価が必要です。
A3.
はい、特に脳の病気が背景にある場合、めまいは一過性に治まっても再発することがあります。違和感が残る場合は早めにご相談ください。
A.
必要に応じてMRI検査を行いますが、検査にかかる時間は15分程度です。
A1.
耳症状(耳鳴り・難聴など)を伴う場合は耳鼻科、伴わない、あるいは脳や神経の病気が疑われる場合は神経内科の受診が適しています。
A.
はい。軽微な脳梗塞(TIA)などが隠れていることがあるため、早期相談をおすすめします。
A.
はい。「歩きづらさ」の原因によってはリハビリ中心で歩行機能の改善が期待できる場合も多くあります。また、「力が入りにくい」場合も原因に応じたリハビリプログラムが効果的ですので、診断に基づいてご案内します。
A.
神経学的診察に加え、MRI検査や神経伝導検査などを症状に応じて行います。
MRI検査は約15分、神経伝導・筋電図検査はそれぞれ30~60分程度を予定しています。
A.
加齢に伴う変化もありますが、神経系の病気が原因のこともあります。変化を感じたら早めにご相談ください。
A.
認知症のタイプによりますが、正常圧水頭症や甲状腺機能低下症などは、治療により症状の改善が見込めます。その他の場合でも、進行を遅らせ、生活の質を保つサポートが可能です。
A.
健康チェックという形で自然に誘導する方法をご提案します。ご家族のみのご相談も受け付けております。
A.
初診時の検査・問診でおおまかな診断は可能ですが、経過観察を経て確定する場合もあります。
A.
急性期の状態が安定したら、できるだけ早く開始するのが理想です。当院では在宅リハビリテーションのご案内も可能です。
A.
はい。一時的でも「手足のしびれ」「ろれつが回らない」などの症状があれば、「一過性脳虚血発作(TIA)」の可能性もあるため、早めの診察をおすすめします。
A.
はい。血圧・血糖・コレステロールの管理によってリスクは大幅に下げることが可能です。健康診断後のご相談も承っています。
A.
非常に重要です。運動習慣を保つことは、筋力やバランスを維持し、日常生活の自立度を高める助けになります。
A.
はい。進行性の病気であるため、継続的な内服管理が必要です。ただし、症状や副作用に応じて薬の種類・量は調整できます。
デバイス療法では、脳深部刺激療法(DBS)レボドパカルビドパ経腸療法、持続皮下注療法もありますが薬は併用です。
A.
MRIや血液検査だけでは確定できないため、神経学的診察と症状の経過、薬剤への反応、必要であれば心筋シンチ、DATシンチなどを組み合わせて診断します。
※心筋シンチ DATシンチは総合病院で検査をお願いしています。
A.
睡眠不足、飲酒、ストレスなどが発作の引き金になることがあります。規則正しい生活、服薬の継続、医師との定期的な連携が大切です。
A.
発作の種類やコントロール状況によります。
長期間発作がない状態が続けば、薬の減量や中止を検討できる場合もあります。ただし、自己判断で中断すると再発のリスクが高まります。
A.
はい。初発の発作であっても、背景にてんかんが潜んでいる可能性があります。
特に10代~40代の方で発作が見られた場合は、早めの受診をおすすめします。
A.
「歩きづらい」「手が震える」「声が出にくい」など、小さな変化でも続く場合は早めの受診をおすすめします。
A.
はい。純粋小脳型では、バランスや歩行などの運動機能に対するリハビリが有効だとされ、終了後もしばらく効果が持続することがあります。
A.
一部のタイプは遺伝しますが、多くの方は遺伝と関係のない孤発性です。診察時にご家族の病歴などを確認し、必要に応じて遺伝子検査も検討します。
A.
放置すると筋力の低下や呼吸障害が進行する可能性があります。治療により進行を緩やかにし、生活の質を保つことができます。
A.
筋萎縮性側索硬化症(ALS)は多くの場合、遺伝しません。
一部に家族性ALSがあります。球脊髄性筋萎縮症(SBMA)は遺伝性疾患ですが、限られた範囲です。
A.
初期は症状があいまいなことも多く、確定診断には複数の検査と経過観察が必要です。神経内科専門医による評価が重要です。
A.
抗AQP4抗体の血液検査、病変の部位、症状の出方などを総合的に判断します。
A.
個人差はありますが、放置すると再発しやすくなります。再発予防の治療継続が重要です。
日頃はない目のかすみや感覚鈍麻、めまいなどが再発のサインでもあります。
いつもと違うと思ったら気にし過ぎと思わずにすぐ相談することが障害(後遺症)にならない・程度を軽くするため大切です。
A.
現時点では根本治療はありませんが、薬で再発を抑えたり、進行を遅らせることができます。
A.
はい。筋力の維持や関節の拘縮予防、日常生活動作のサポートとして重要です。
A.
慢性の経過をたどることが多いですが、治療により症状を安定させることは可能です。再発にも注意が必要です。
A.
中高年にやや多いとされますが、年齢や性別に関わらず発症する可能性があります。
A.
MRIは構造の異常を見つけるにはとても優れた検査ですが、神経の働きや生活習慣の癖や乱れといった“機能の問題”までは映し出すことができません。
様々な症状の臨床形を学んでいる神経内科専門医は、個々の症状の特性や原因を特定するために、患者さまの訴えや症状、過去の病歴、生活習慣などを詳細に分析した上で、必要な範囲のMRI検査を行うことで、適切な診断と治療法の選択につなげていくことができます。
A.
はい。初診当日にMRI検査を行い、同日に結果説明が可能です。
MRI検査は、ペースメーカーや人工内耳、脳動脈クリップなどの禁忌の患者さま以外であれば、原則的に当日検査が可能です。
ただし、検査を行うか否かは、当院の医師が診察で判断させていただきます。
A.
適応の有無を含めて診察後の判断となります。適応の場合は2回目の受診で実施いたします。
A.
はい。接種は可能です。ただし、ワクチンの在庫によりますので、事前にお問い合わせの上、ご来院ください。

