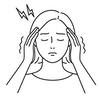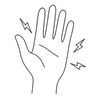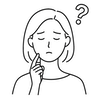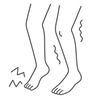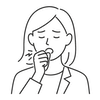「ふるえ」の原因は
年齢だけじゃない!?
神経のはたらきを診ながら、
正確な診断とケアをご提案します

最近、手がふるえることが増えたかも…
そんな小さな変化に気づいたら。
手や体のふるえは、
年齢に関係なく誰にでも起こる可能性があります。
しかし、中には治療が必要な病気の初期サイン
であることも少なくありません。
ふるえにはさまざまな原因があり、
症状のタイプや経過によって、適切な診断と対応が異なります。
神経内科専門医の視点で、しっかり原因を見極めることが大切です。
受診の目安
以下のような症状がある場合は、神経内科の受診をおすすめします。
□手や体が自然にふるえることが増えた
□動作のたびに手が震える
□静止時にも手足がふるえる
□歩きにくさや動作の遅さも感じる
□家族からふるえを指摘された
これらの症状に限らず、
ささいな「ふるえ」でも、気になったときは、
まず神経内科専門医にご相談ください。
ふるえの
原因と分類
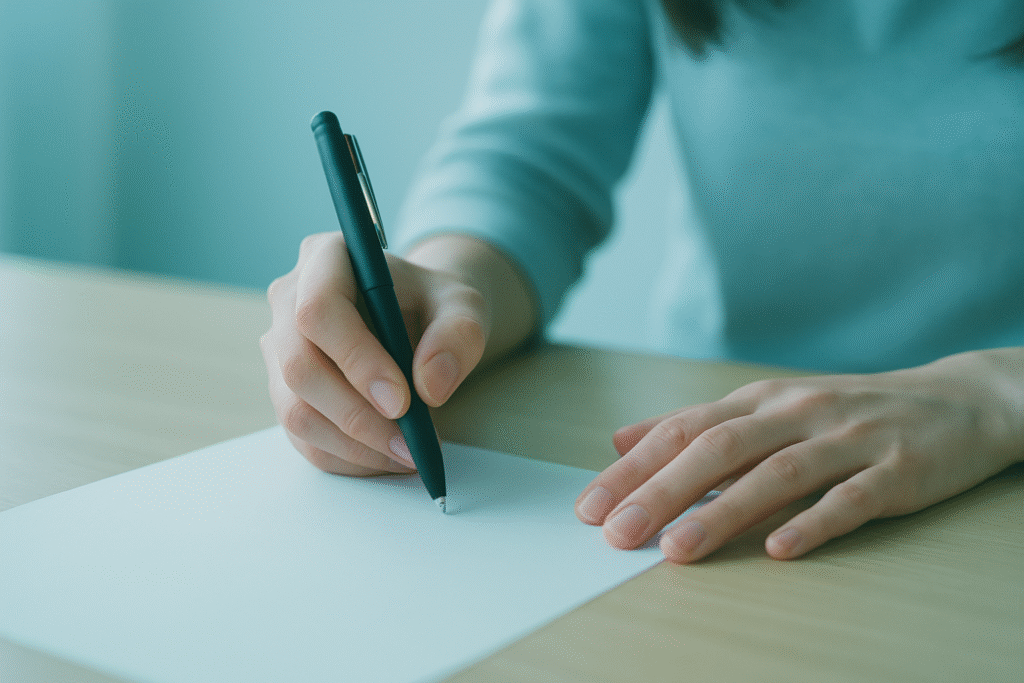
ふるえは、医学的には「振戦(しんせん)」と呼ばれ、
大きく以下のように分類されます。
本態性振戦(ほんたいせいしんせん)
原因が明確にはわからないふるえで、
コップを持つ、文字を書くなどの動作で
手がふるえることが特徴です。
家族に同じ症状を持つ方がいる場合もあり、
比較的頻度の高いふるえです。
【パーキンソン病に伴うふるえ】
じっとしているときに手足がふるえる
「静止時振戦」が特徴です。
ふるえに加えて、動作が遅くなる、
筋肉が固くなる、バランスを崩しやすくなるなど、
さまざまな症状が進行性に現れます。
→ パーキンソン病についてもっとくわしく
【脳卒中後のふるえ】
脳出血や脳梗塞などの脳血管障害によって
脳が損傷された後に、手足のふるえが現れることがあります。
しびれや力の入りにくさを伴う場合もあります。
→ 脳血管障害についてもっとくわしく
【内科的疾患によるふるえ】
●甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)
甲状腺ホルモンの異常によって代謝が活発になり、
手指が細かく震えます。
●低血糖発作
血糖値が急激に低下することで、
ふるえ・動悸・冷や汗が生じます。
●薬剤性ふるえ
一部の薬剤(抗うつ薬、気管支拡張薬など)が
副作用としてふるえを引き起こすことがあります。
神経内科専門医による
診断の特徴
ふるえの診断では、「どのような場面でふるえるのか」を
丁寧に見極めることが重要です。
大阪・都島の氷室クリニックでは、
□詳細な問診(いつ、どのようなふるえか)
□神経学的診察(他の神経症状の有無)
□必要に応じて脳MRI検査、血液検査(甲状腺機能など)
を行い、ふるえの背景にある病態を総合的に診断します。
ふるえの種類を正確に見極めることが、
その後の治療方針を決めるうえで非常に重要です。
→ MRI+神経生理検査についてもっと詳しく
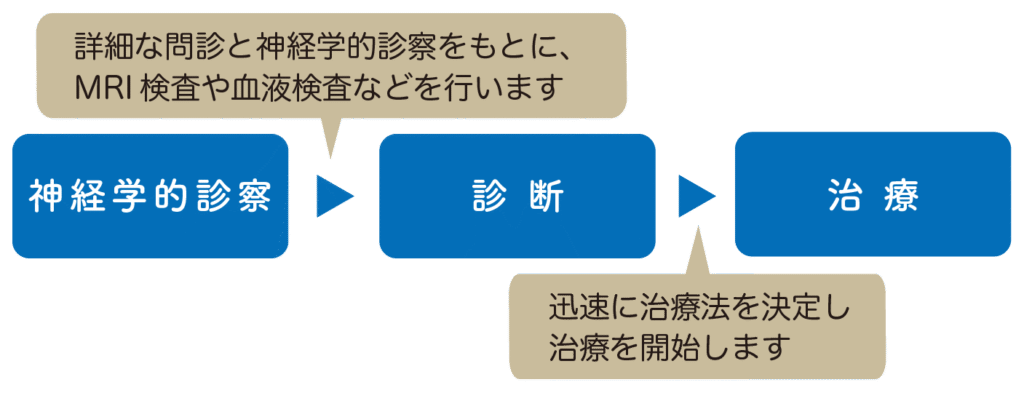
ふるえの治療法と
生活へのアドバイス

ふるえの治療は、原因に応じて異なります。
【本態性振戦によるふるえ】
必要に応じて抗振戦薬(プロプラノロールなど)を使用します。
【パーキンソン病によるふるえ】
ドパミン補充療法を中心とした薬物治療が行われます。
【内科疾患によるふるえ】
基礎疾患(甲状腺機能亢進症、低血糖など)への適切な治療が必要です。
日常生活では、
□ストレスをためすぎない
□規則正しい生活を心がける
□症状に応じて動作を工夫する
などが、ふるえのコントロールに役立ちます。
よくある質問(FAQ)
Q1.
ふるえは年齢のせいではないのでしょうか?
A1.
年齢に伴う軽いふるえもありますが、ひどくなっている場合や、日常生活に支障をきたす場合は、神経内科の受診をおすすめします。
Q2.
すべてのふるえがパーキンソン病なのでしょうか?
A2.
いいえ、本態性振戦や内科疾患、薬剤性など、ふるえの原因は多岐にわたります。専門的な診断が重要です。
Q3.
ふるえだけでも受診できますか?
A3.
はい、ふるえは神経内科でよく扱う症状の一つです。お気軽にご相談ください。