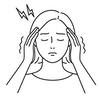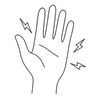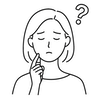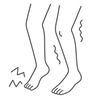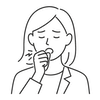その手のふるえ
「年齢のせい」
だと思っていませんか?

中年以降で、手のふるえや
歩きづらさを感じている方の中には、
パーキンソン病の可能性がある場合があります。
特に以下のような症状が重なる時は、
注意が必要です。
□動き出しが遅くなる
□手の振りが減る
□表情がこわばる
□動作が遅い(時間がかかるようになった)
パーキンソン病は進行性の神経疾患ですが、
現在では治療によって症状をコントロールできる時代
になっています。
「もしかして…」という不安をお持ちでしたら、
まずは神経内科専門医にご相談ください。
パーキンソン病とは?

パーキンソン病は、
脳内の神経伝達物質「ドパミン」が減少することで起こる、
主に運動機能に影響を及ぼす病気です。
発症の原因はまだ完全には解明されていませんが、
中年以降の方に多く、ゆっくりと進行するのが特徴です。
代表的な症状には以下があります。
□じっとしていても手がふるえる(安静時振戦)
□動作がゆっくりになる(動作緩慢)
□体がこわばる、筋肉が突っ張る(筋強剛)
□歩幅が狭くなり、すり足になる(小刻み歩行)
□表情が乏しくなる(仮面様顔貌)
など
こうした症状は、
「年齢のせいかな」と見過ごされやすいですが、
早期発見・早期治療がとても大切です。
神経内科での
診断と治療の特徴

パーキンソン病は、
画像検査(MRI)だけでは診断が難しい病気です。
神経内科では、診察を通じた神経学的評価や、
必要に応じた薬の反応を見る「診断的治療」などを
組み合わせた上で、慎重に診断を進めます。
大阪・都島の氷室クリニックでは、
院内のMRI、必要に応じて院外での心筋シンチ、
DATスキャンなどの検査に加え、
丁寧な問診・診察を通して、
病気のステージや重症度を把握し、
最適な治療方針を立てていきます。
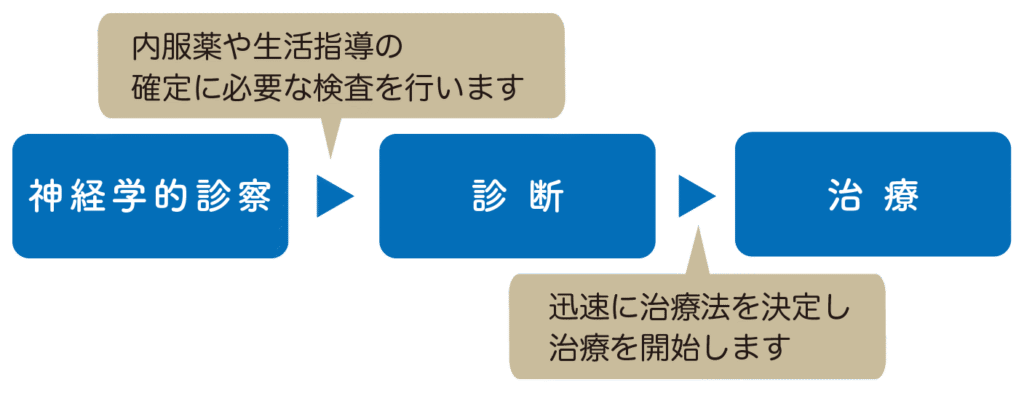
パーキンソン病の
治療とケア

パーキンソン病は、現時点では根治的な治療法はありません。
しかしながら、脳内で減少したドパミンを補う薬剤により、
症状を大きく改善・安定させることが可能です。
主な治療法は以下の通りです。
□レボドパ製剤(ドパミンを補う基本薬)
□ドパミン作動薬、MAO-B阻害薬、COMT阻害薬などの補助薬
□薬の効果が不安定になった場合のタイミング調整
□生活リズムの見直しや、転倒予防指導
□必要に応じてリハビリテーションや嚥下・言語訓練の導入
□非運動症状への対応(便秘・起立性低血圧・レム睡眠行動異常症など)
薬の選択と調整には、専門的な知識と経験が不可欠です。
また、症状の変化に応じてきめ細かなフォローが求められるため、
診察の頻度や対応の柔軟さも重要となります。
大阪・都島の氷室クリニックでは、
日常生活に直結する運動症状だけでなく、
非運動症状も含め、
総合病院よりもこまめに診察できる体制
を整えています。
発症初期の方から進行期の患者さままで
幅広い病期の方が通院されています。
よくある質問(FAQ)
Q1.
パーキンソン病はどんな検査で診断できますか?
A1.
MRIや血液検査だけでは確定できないため、神経学的診察と症状の経過、薬剤への反応、必要であれば心筋シンチ、DATシンチなどを組み合わせて診断します。
※心筋シンチ DATシンチは総合病院で検査をお願いしています
Q2.
薬はずっと飲み続けなければいけませんか?
A2.
はい。進行性の病気であるため、継続的な内服管理が必要です。
ただし、症状や副作用に応じて薬の種類・量は調整できます。
デバイス療法では、脳深部刺激療法(DBS)、レボドパカルビドパ経腸療法、持続皮下注療法もありますが、薬は併用になります。
Q3.
リハビリや運動も効果がありますか?
A3.
非常に重要です。運動習慣を保つことは、筋力やバランスを維持し、日常生活の自立度を高める助けになります。
小さな症状の確認を積み重ねることが、
正確な診断への鍵となります。
まずはお気軽にご相談ください。