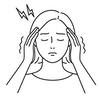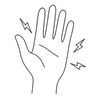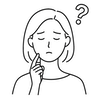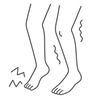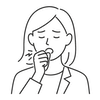認知症専門医が診る「MCI(軽度認知障害)」とは?
【監修】氷室クリニック院長・氷室公秀(医学博士・神経内科専門医・認知症専門医)
最近、テレビCMなどで
よく耳にするようになった
「MCI(エムシーアイ)」。
「名前は知っているけれど、
詳しくは知らない」
という方も多いのではないでしょうか。
MCIとは
「Mild Cognitive Impairment」の略で、
「軽度認知障害」のこと。
認知症の前段階にあたる状態で、
健常と認知症の“あいだ”
に位置づけられます。
今回は、この「MCI」について、
わかりやすくお伝えしていきます。
CONTENTS
1.MCI(軽度認知障害)とは?
2.認知症との違い
3.MCIを見分ける5つのチェックポイント
4.認知症の代表的な3疾患におけるMCIでの違いについて
5.MCIが注目される理由
6.MCIと診断されたらできること
7.認知症専門医に相談するメリット
8.MCIは「まだ間に合う」のサイン
1.MCI(軽度認知障害)とは?
MCIは、健常と認知症の中間にある
“グレーゾーン”の状態を指します。
□記憶力や注意力の低下はあるものの、
日常生活はおおむね自立して送れる
□認知症へ進行するリスクは高いが、
生活習慣の見直しにより改善するケースもある
数値で見るMCI
●65歳以上の約15~20%がMCIと推定されています【Alzheimer’s Association 2021】
●MCIの人のうち、年間10~15%が認知症に進行すると報告されています【Petersen RC, 2018】
●一方で、30~40%は改善するケースもあります【Roberts R, 2014】

2.認知症との違い
MCIは…
✅ 記憶や判断力に軽度の障害がある
✅ 社会生活や日常生活に大きな支障はない
認知症は…
✅ 記憶障害や見当識障害、判断力低下がみられる
✅ 金銭管理や買い物、服薬管理など日常生活に支障が出る
数値的な比較
●認知症の有病率は、65歳以上で約8人に1人(12~13%)
●85歳以上では3人に1人が認知症に罹患していると推計されています【厚生労働省, 2023年推計】
つまり、MCIの段階で気づくことが、将来の認知症リスクを左右するカギとなります。
3.MCIを見分ける5つのチェックポイント
以下のような症状が
複数当てはまる場合は
注意が必要です。
ただし、当てはまるからといって、
必ず「MCI」や「認知症」に
なるわけではありません。
大切なことは、
「気づきのサイン」を見逃さず、
専門医の診断・評価を受けることです。
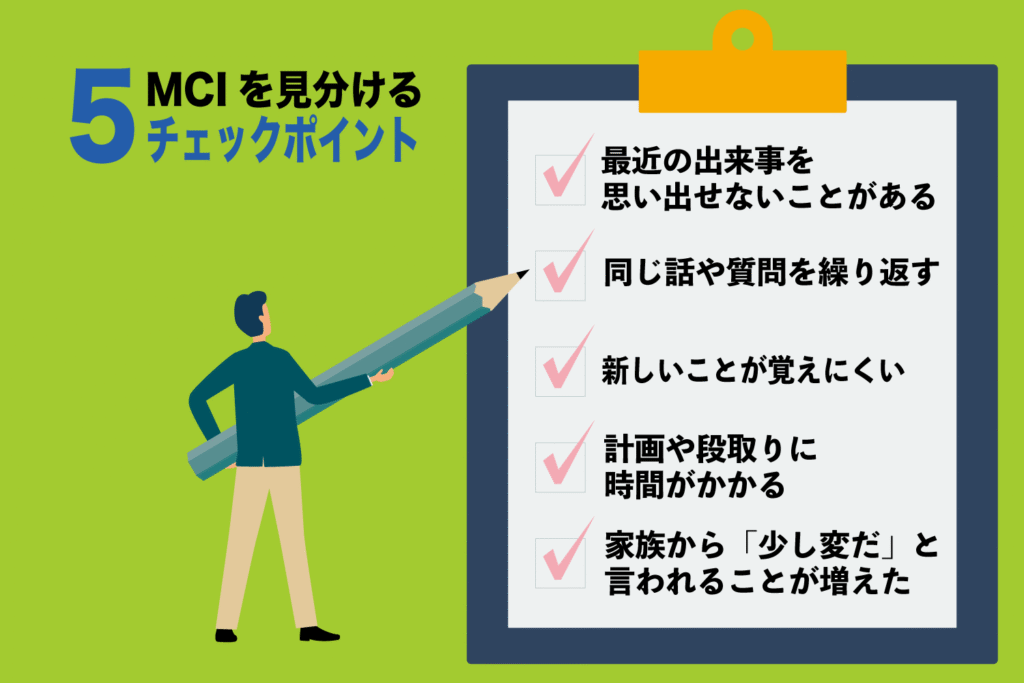
※上記の症状は「MMSE(Mini Mental State Examination)」や「MoCA(Montreal Cognitive Assessment)」などの認知機能検査でも確認されます。
※特にMoCAはMCIの検出感度が約90%と高く、世界的に広く利用されています【Nasreddine ZS, 2005】。
4.認知症の代表的な3疾患における
MCIでの違いについて
「気づきのサイン」は、
認知症の疾患によっても異なります。
①アルツハイマー型MCI
→「もの忘れが目立つ」
②レビー小体型MCI
→「注意や視覚の問題・症状の波・幻視」
③前頭側頭型MCI
→「性格変化や行動異常・言語障害」
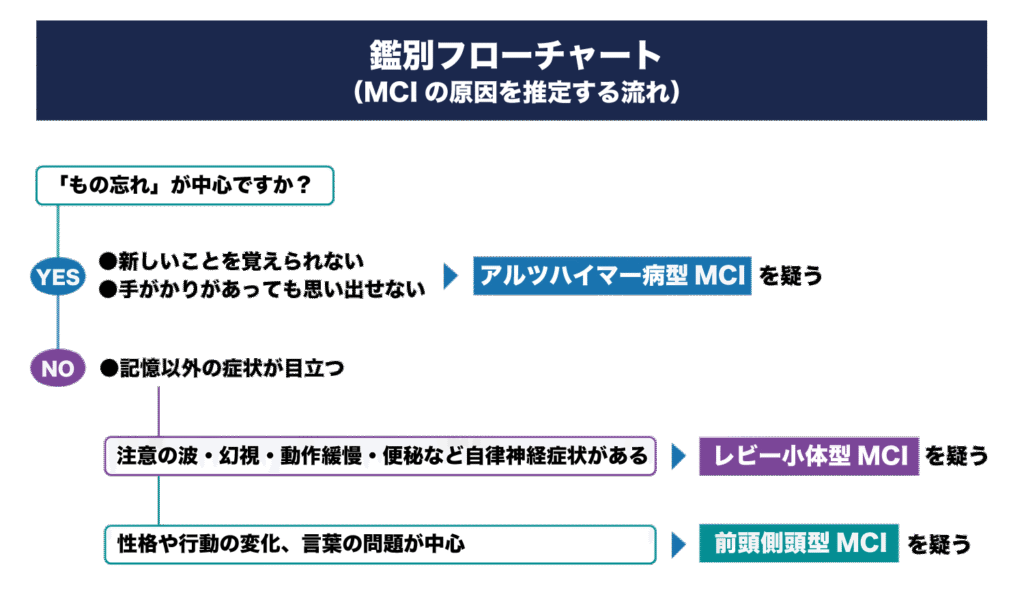
これらの違いは、ご本人よりもご家族が
気づかれる場合が多々あります。
そこで、疾患別に家族が気づきやすい行動を
チェックリストにしてみました。
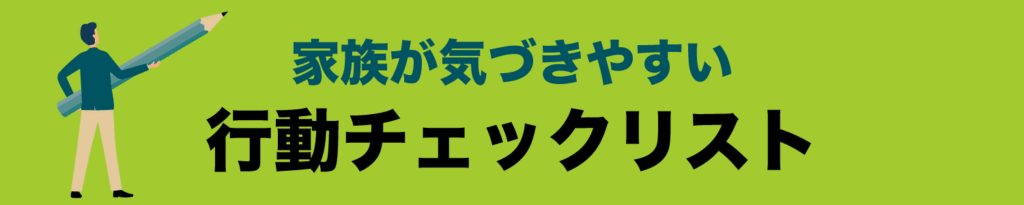
①アルツハイマー病型MCI
✅ 最近の出来事をすぐに忘れる
✅ 同じ質問を繰り返す
✅ カレンダーやメモを見ても思い出せない
✅ 本人も「もの忘れが増えた」と自覚している
②レビー小体型MCI
✅ 調子の「良い日」と「悪い日」の差が大きい
✅ 見えないはずの人や動物が「見える」と言う(幻視)
✅ 集中力が続かず、会話が途切れがち
✅ 小刻み歩行や手の震えなどパーキンソン症状がある
✅ 便秘や立ちくらみなど自律神経の不調がある
③前頭側頭型MCI
✅ 性格が変わったように感じる(頑固、無関心、子供っぽくなる)
✅ 他人への配慮が減る(失礼な発言、ルールを守らない)
✅ 衝動的な行動(過食・同じ行動の繰り返し)
✅ 言葉が出にくい、語彙が減る、会話が単調になる
✅ 物忘れ」よりも「行動や言葉の異常」が目立つ
5.MCIが注目される理由
最近になってMCIが注目されてきたのは、
認知症の早期発見・予防につながるからです。
●新薬(例:レカネマブ)は「早期アルツハイマー病(MCIを含む段階)」に投与することが前提になっています。
●治療の有効性を示す研究も「軽度段階での診断」が重要であることを示しています。
●日本でも「健診での認知機能評価」や「地域での早期発見」への取り組みが進んでいます。

6.MCIと診断されたらできること
MCIは「必ず認知症になる」
というものではありません。
実際に、生活習慣を見直すだけで、
改善する方もいらっしゃいますし、
認知症予防の観点からも効果があります。
生活習慣による予防・改善効果
●毎日のウォーキングなどの適度な運動
※週150分以上の中強度の有酸素運動で認知機能低下リスクが有意に減少【Lautenschlager NT, 2008】
●野菜・魚・オリーブオイルを取り入れたバランスの良い食事
※地中海式食事(緑黄色野菜・魚・オリーブオイルの多い食事)が進行抑制に有効【Scarmeas N, 2006】
●しっかり睡眠をとる
※1日7時間前後の睡眠が理想的とされ、不眠や過眠はリスク因子
●趣味や地域活動などの人との交流
※交流や趣味など社会的活動が多い人は認知症発症率が低い【Fratiglioni L, 2004】
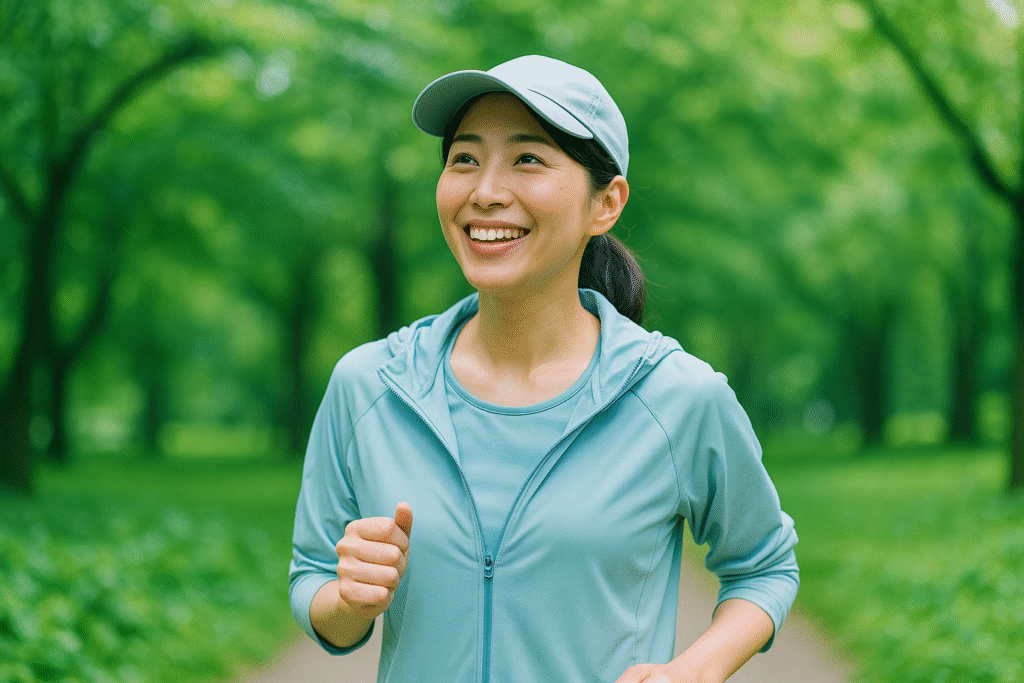
7.認知症専門医に相談するメリット
「年のせいかな」と思って放っておくことは、
認知症予防の機会を見逃すことにもなります。
気になることがある場合は、
認知症専門医によるMCIの診断・評価を
受けるようにしましょう。
●MRI検査
脳の状態を検査し、脳萎縮(特に海馬の萎縮)の有無を確認します。
●血液検査
他の病気による物忘れ(甲状腺疾患やビタミン欠乏などによる可逆性の認知機能障害)を除外します。
●神経心理検査
MoCAや長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)など、認知機能検査(簡単な質問や図形のテスト)で客観的に評価します。
こうした評価により、
「認知症のリスクがあるMCI」なのか、
「加齢に伴う健忘」なのかを区別できます。

8.MCIは「まだ間に合う」のサイン
いま現在、65歳以上の
約15~20%がMCIだと言われています。
そのうち、
年間10~15%が認知症に進行する一方、
改善する人もいらっしゃいます。
ということは、
早期診断と、適切な生活習慣が、
将来の健康寿命を大きく左右する
ことにつながります。
「最近忘れっぽい気がする」
「家族の様子が少し気になる」
そんなときは、自己判断せず、
早めに認知症専門医にご相談ください。