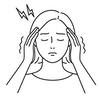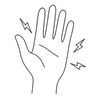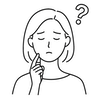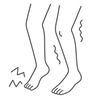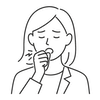【監修】氷室クリニック院長・氷室公秀(医学博士・神経内科専門医・認知症専門医)
Contents
- よくある「めまい」…カラダからの大切なサインかも!
- 「めまいの感じ方」からわかる原因のちがい
- グルグルと目が回る(回転性めまい)
- フワフワとふらつく(浮動性めまい)
- 高齢者に多い「めまい」にも要注意
- 神経内科専門医の「めまい」精密診断
- こんな「めまい」は、すぐ神経内科に相談を!
- 「めまいくらい…」と思わないことが大切です
よくある「めまい」…
カラダからの大切なサインかも!
急に目の前がグルグル回り始めた!
フワフワしてまっすぐ歩けない!
こんな「めまい」を経験したことはありませんか?
実は「グルグルと回るめまい」と「フワフワするめまい」とでは、体の中で起こっている異常がまったく異なるのです。
めまいは比較的よくある症状ですが、危険な病気のサインである場合もあります。
だからこそ、早めにめまいの種類を丁寧に見極め、その原因に合わせた治療を行うことが大切です。
「めまいの感じ方」からわかる
原因のちがい

比較的若い方に多いめまいは、主に次の2タイプに分けられます:
1.グルグルと目が回る(回転性めまい)
「回転性めまい」は、三半規管や耳石器(内耳)**の異常によることが多く、「耳からくるめまい」とも言われます。
代表的な疾患
□良性発作性頭位めまい症(頭の動きに伴って起きる)
□メニエール病(めまい+耳鳴り・難聴を繰り返す)
□前庭神経炎(ウイルス感染による急性のめまい)
□突発性難聴(聴力低下とめまいが同時に起こる)
□薬剤性前庭障害(特定の薬剤による影響)
突然の激しいめまい発作として現れることが多いのが特徴です。
2.フワフワとふらつく(浮動性めまい)
「浮動性めまい」は、脳(特に小脳・脳幹)や自律神経のトラブルが原因のことが多く、「脳からくるめまい」に分類されます。
代表的な原因
□軽度の脳梗塞・脳出血
□椎骨脳底動脈循環不全(脳への血流不足)
□ごくまれに脳腫瘍
「地に足がつかない」「歩くとフラつく」といった感覚が続く場合は、神経系の精密検査が必要です。
高齢者に多い「めまい」にも要注意
高齢の方では、回転性・浮動性どちらにも当てはまらない「あいまいなフワフワ感」が続くことがあります。
代表的な原因
□加齢にともなう平衡感覚の低下
□起立性低血圧や脱水
□小さな脳梗塞や慢性的な血流不足
□薬の副作用や多因子性めまい
などが挙げられます。
「年齢のせい」と軽く考えず、専門的な診察が大切です。
いずれにしても、経験したことのない激しいめまい、麻痺や言語障害を伴う場合は、早急な対応が必要です。
神経内科専門医の
「めまい」精密診断

“脳や神経の異常”を丁寧に見極める
「めまいがする=耳の病気」と思われがちですが、
実際には脳や神経のトラブルが背景にあるケースも少なくありません。
たとえば──
小さな脳梗塞や脳出血の前兆
→ ごく軽度の脳血管障害では、画像検査に映らないことがありますが、めまいという症状だけが初期のサインになっていることがあります。
神経伝達の異常による平衡感覚の障害
→ 三半規管や視覚、筋肉の感覚などから得た情報は、脳内で統合されてバランスを取っています。この伝達過程のどこかにトラブルがあると、「フワフワする」「足が地につかない」ような感覚が生じます。
→ これは神経内科での神経学的検査や歩行評価などで初めて気づくことが多い異常です。
ストレスや生活習慣の癖や乱れが引き起こす慢性的なふらつき
→ 「検査では異常なし」とされがちですが、日常的なストレスや睡眠不足、疲労によって自律神経の働きが乱れると、慢性的な浮動感や不安定な状態が続くことがあります。
→ 神経内科では、ストレスや生活習慣からもアプローチしながらその背景に迫ります。
MRI検査では原因が見つからない!
そんな方こそ神経内科へ
CTやMRIなどの画像検査は、
確かに大きな異常の発見には有用です。
しかし実際の臨床では、
「画像では異常なし」とされても、
神経内科専門医が神経学的所見や問診から
原因を見つけるケースが多くあります。
たとえば──
□視線の動き(眼振)の観察
□姿勢保持や歩行の安定性の評価
□手足の協調運動や筋力チェック
□自律神経機能の乱れを示すサインの有無
こうした評価は、
脳と神経の専門医である神経内科専門医だから
対応できる領域でもあります。
こんな「めまい」は、
すぐ神経内科に相談を!

以下のような症状がある場合は、
早めに神経内科を受診してください。
✅ 今までにない激しいめまい
✅ フラついて立てない
✅ めまいと同時にしびれや言語障害がある
✅ 耳鳴り・難聴を繰り返す
✅ 疲労やストレスでフワフワ感が増す
めまいの持続時間が短くても、
繰り返す場合は注意が必要です。
「なんとなくおかしい」と感じることこそ、
体からの大切なサインです。
「めまいくらい…」
と思わないことが大切です

「少し休めば治るかな」
「年のせいかも」
そういった思い込みは危険です。
大阪・都島の氷室クリニックでは、
神経内科専門医がすべての診療にあたり、
耳・脳・神経・自律神経の視点から総合的に診断します。
「異常がない」と言われたけれど、症状が続く…。
そんな不安や不調に寄り添うことができるのも、
神経内科の役割です。
必要に応じて、
ストレスや生活習慣の面からもサポートしながら、
患者さま一人ひとりの
「なぜ起こっているか?」
を大切に診療を行っています。