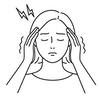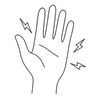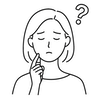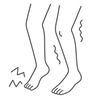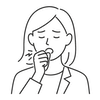【監修】氷室クリニック院長・氷室公秀(医学博士・神経内科専門医・認知症専門医)
Contents
- MRI検査で異常なし。でも頭痛が続く…
- 脳の“機能の異常”は、MRIには映らない!
- 片頭痛とは?
- 頭痛プロファイリング+MRI MRIを“読む”頭痛診療
- 神経内科専門医の頭痛の分類例
- 神経内科のMRI検査
- 一人ひとり異なる頭痛の“治し方”
- 「この痛みの正体を知りたい」そう思ったら
MRI検査で異常なし。
でも頭痛が続く…
最近は、「頭痛と言えば検査」
と思っておられる方が増えてきました。
近隣の頭痛外来でMRI検査を受け、
「異常がない」と言われると、
ほっとして帰られる方も多いそうです。
ですが、MRI検査で“異常なし”と診断されても、
痛みや不快感が治まる訳ではありません。
そこには、神経の働きやストレス、
生活習慣の癖や乱れといった
“MRIには映らない原因”
が関係している可能性があるからです。
大切なのは、
「異常がない=問題ない」とは限らない、
ということ。
当院では、MRIに映らない“機能の異常”にも
しっかりとアプローチして、
頭痛の原因として見逃さないよう努めています。
「どうして痛いのかわからない」
そんなお悩みに、一緒に向き合っていく。
これも神経内科専門医の役割のひとつと考えています。
脳の“機能の異常”は、
MRIには映らない!

脳の病気には、「構造の異常(脳出血・脳腫瘍など)」と
「機能の異常(神経の働きの乱れ)」の2種類があります。
MRIは構造の異常を見つけるにはとても優れた検査ですが、
神経の働きや生活習慣の癖や乱れといった
“機能の問題”までは映し出せません。
たとえば、よくある片頭痛などは、
MRIの画像には何も映らないのです。
片頭痛とは?
片頭痛は、頭の片側または両側に
ズキンズキンと脈打つような痛みが出る頭痛です。
この発作的な痛みは、
「三叉神経(さんさしんけい)」という神経が
強く興奮することで始まります。
なぜ三叉神経が興奮するの?
次のようなさまざまな要因が
三叉神経の興奮を引き起こすと考えられています:
□遺伝的な体質
□女性ホルモンの変動(月経の前後や更年期など)
□天気の変化(特に気圧の低下)
□ストレスや疲れ
□飲酒やチョコレートなど、一部の食べ物
こうした刺激で三叉神経が過敏になると、
□視界にキラキラした光が見える(閃輝暗点)
□音や光がつらく感じる(感覚過敏)
□前額部のに鈍い痛みを認める(三叉神経の炎症))
などの前ぶれ(前兆)が出ることがあります。
痛みのピークに至る仕組み
三叉神経が興奮すると、
「CGRP」という物質が放出され、
神経がさらに刺激されます。
これが引き金となって、
脳の血管が拡がり、
その拍動によって痛みが発生します。
この流れが、片頭痛のメカニズムとされています。
片頭痛の予防と治療法
● 日常生活でできる予防
片頭痛は完全に防ぐことが難しい場合もありますが、
次のような生活習慣の見直しが予防につながります。
□睡眠時間をしっかり確保する
□ストレスをためない工夫をする
□お酒の飲みすぎや片頭痛を誘発する食べ物を控える
● 予防のための薬
症状が頻繁に出る場合は、
医師と相談しながら予防薬を使うことがあります。
□抗てんかん薬や抗うつ薬(ストレスや神経の過敏さを抑えます)
□カルシウム拮抗薬やβ遮断薬(血管の過剰な拡張を防ぎます)
□抗CGRP抗体薬(三叉神経の興奮そのものを抑える新しい治療法です)
● 発作が起きたときの治療
痛みが出たときには、できるだけ早めに
次のような薬を使うことが効果的です。
□痛み止め(消炎鎮痛剤)
□トリプタン系薬剤:拡がった血管を収縮させて痛みを抑えます。
片頭痛は遺伝!?
三叉神経が関係する片頭痛は、
遺伝的な傾向が強い頭痛のひとつです。
ご両親のどちらかが頭痛持ちの場合、
その体質を受け継ぐことが少なくありません。
この遺伝的な要素に加え、
ホルモンバランスの変化(特に女性では初潮以降)や、
ストレスなどの環境要因がきっかけとなって、
片頭痛が起こることがあります。
また、働きはじめた後など、
生活のリズムや負担が変わる時期に
症状が目立つようになる方もいます。
症状が強い場合には、学校や仕事に支障をきたし、
日常生活の質(QOL)が大きく下がってしまうこともあるため、
適切な診断と治療が重要です。
頭痛プロファイリング+MRI
MRIを“読む”頭痛診療

頭痛の診療で大事なことは、
多種多様な頭痛の臨床形を知っていて、
その鑑別に合わせたMRI画像検査が行えるかどうかです。
たくさんの頭痛の臨床形を学んでいる神経内科専門医は、
個々の頭痛の特性や原因を特定するために、
患者さまの訴えや症状、過去の病歴、生活習慣などを
詳細に分析します。
その鑑別を考えたうえで画像検査を行うことにより、
適切な診断と治療法の選択につなげていきます。
いわば、頭痛のプロファイリングですね。
神経内科専門医の
頭痛の分類例

「片頭痛」「緊張性頭痛」「群発頭痛」
などの慢性頭痛は「一次性頭痛」と呼ばれ、
他に原因となる病気がなく、
頭痛自体が治療の対象となります。
一方、脳出血や脳腫瘍など、
何らかの病気の症状として起こる頭痛は
「二次性頭痛」と呼ばれ、
命にかかわるような疾患が原因の場合があります。
一般的にMRI検査は、
この二次性頭痛を発見、
および頭痛の原因から除外するために行われます。
神経内科のMRI検査
神経内科では、
前述のプロファイリングに基づき、
検査範囲を特定してから撮影を行います。
たとえば
●「クラウンドデンス症候群(crowned dens syndrome)」(偽痛風が原因で起こる頭痛)が疑われる場合
→首の上の方(上部頚椎)までしっかりと撮影できるようにMRIの範囲を広げて、関節の周囲に炎症や腫れがあるかを確認します。
また、いわゆる「一次性頭痛(特定の原因が見つからない頭痛)」でも、画像検査が役立つケースがあります。
●低髄圧症(ていずいあつしょう)
→ 横になると楽になり、起き上がると悪化する頭痛
→ 髄膜(脳を包む膜)が厚くなっている様子を見るため、Flair(フレア)という特殊な撮影方法で、複数の角度からMRIを撮影します。
●可逆性脳血管攣縮症候群(かぎゃくせいのうけっかんれんしゅくしょうこうぐん)
→ 突然の激しい頭痛が特徴
→ 最初の発作から数日後に血管が一時的に細くなることがあるため、数日後に再度MRIを撮影して確認します。
●後頭神経痛・緊張型頭痛
→ 首や後頭部の筋肉の緊張(ストレートネック・肩こりなど)によって起こる頭痛
→ この場合は頭だけでなく首(頚椎)のMRIも撮影して、隠れた異常がないかを調べます。
●副鼻腔炎(ふくびくうえん)による頭痛
→ 鼻の奥の空洞(副鼻腔)のうち、蝶形骨洞や前頭洞に炎症があると頭痛の原因になることがあり、それに応じた部位を詳しくMRIで撮影します。
(※なお、上顎洞の炎症では通常は頭痛は起きません)
このように、頭痛の背景にあるさまざまな疾患を見極めるには、疑われる原因に応じて「どこを・どの方法で」検査するかをきちんと選ぶことが重要です。
一人ひとり異なる
頭痛の“治し方”

最近では、頭痛の治療法も進化してきました。
これまでのように「痛くなったら薬を飲む」のではなく、
「痛くならないように予防する」ことが、
今のスタンダードな治し方となっています。
たとえば、
内服薬のタイミングを管理できるアプリを使ったり、
症状が出そうな時期に合わせて注射薬を接種したりと、
予防法はさまざまです。
中でも、片頭痛や群発頭痛のように
日常生活に大きな支障が出るタイプの頭痛では、
必要な治療をしっかり受けることが重要です。
ただし、以下のような注意点もあります。
□毎月1万円以上かかる「CGRP抗体製剤」のように、経済的な負担が大きい治療もあります。
(保険の種類によっては補助が出ることもあります)
□若い女性では、妊娠時に胎児への影響が考えられる「バルプロ酸」という薬は慎重に使う必要があります。
□血圧が低めの方に、カルシウム拮抗薬やβ遮断薬などの予防薬を安易に使うことも避けるべきです。
このように、頭痛の治療は
「その人に合った方法」を選ぶことが大切です。
生活スタイルや体調、ライフステージに応じて、
医師と相談しながら最適な治療を
一緒に見つけていきましょう。
「この痛みの正体を知りたい」
そう思ったら、神経内科専門医へ

現代を生きる人が、
避けては通れないストレスや寝不足、
生活リズムの乱れといった日常の要因が、
頭痛やめまい、しびれといった症状の
背景にあることもあります。
神経内科では、こうした
“からだとこころのつながり”
にも目を向けながら、
診断と治療を進めていきます。
「最近仕事が忙しくなって頭痛の頻度が増えた」(転職や異動を契機とした頭痛)
「突発的な頭痛や、ふわっとしためまい、手足のしびれが気になる」
「薬を飲んでるけど効きにくくなってきた、または効かない」
こんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。
自分の頭痛についてよく知り、
どう対処すればよいかを身につけていくことで、
頭痛は少しずつコントロールできるようになります。
そうすることで、毎日の暮らしもぐっと楽になりますよ。
そのような方々の力になれるのが神経内科専門医だと、
私たちは考えています。